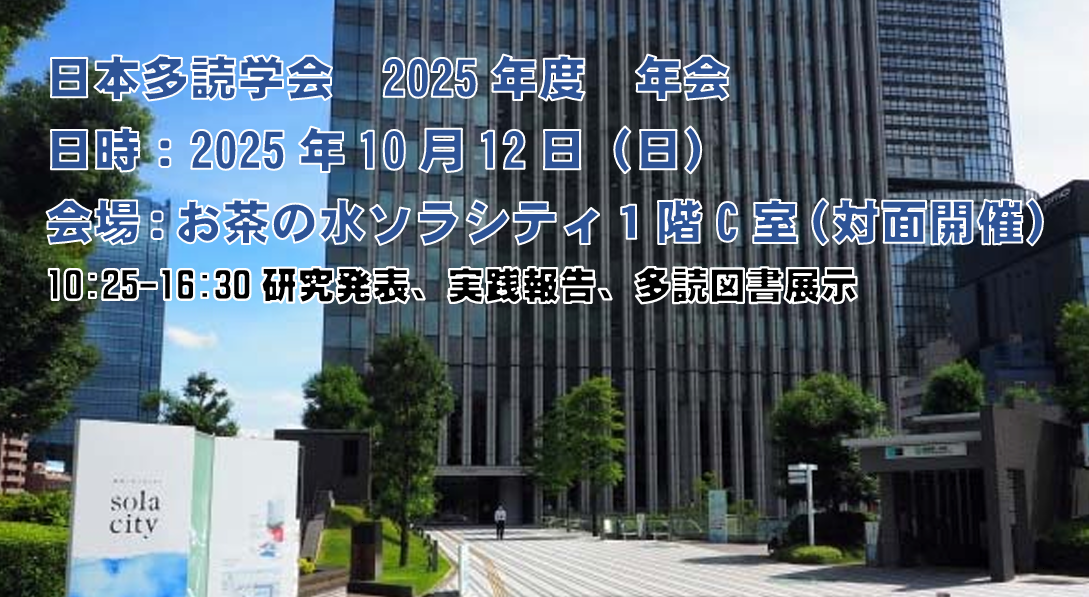
会場:https://plaza.solacity.jp/
-----------------
9:30- 開場、受付開始
10:00-10:20 年次総会(役員名簿、前年度収支報告、本年度予算案の承認)
日本多読学会 2025年度 年会 終わりました
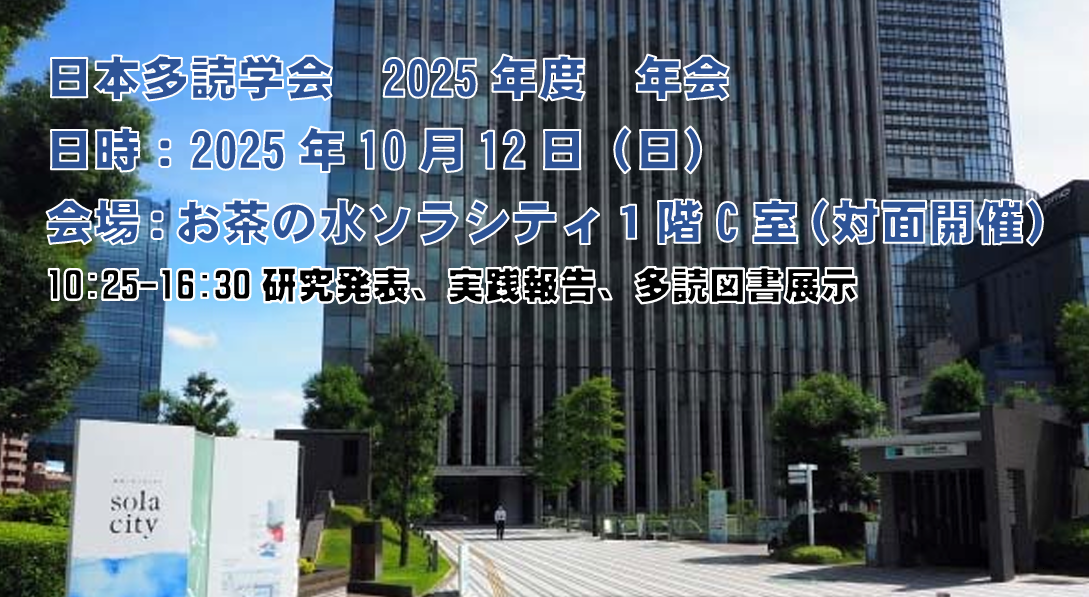
会場:https://plaza.solacity.jp/
-----------------
9:30- 開場、受付開始
10:00-10:20 年次総会(役員名簿、前年度収支報告、本年度予算案の承認)
10:25- 開会・会長あいさつ
10:30-11:00 実践報告 片山 哲太郎(横浜雙葉中学高等学校)
動機付けを意識した多読多聴課題の工夫
高校1年生の英語授業において1年間継続して実施した多読・多聴課題の実践例を報告する。ブックレポートや多聴記録の作成、共有活動、授業通信の配布などを通じて、自発的な学習姿勢の育成と英語への興味の喚起を図った。年度末のアンケートを通して、生徒たちが楽しみながら活動に取り組んでいたこと、英語への関心が高まったこと、実践の効果を実感していたことが伺えた。
11:00-11:30 実践報告 Adam Ezard(早稲田大学【高等学院】(録画映像)
Applying a Blended Learning Approach to Extensive Reading at the Junior
High Level
Junior high school is a great place for students to supplement their English
studies with extensive reading. In order to increase engagement and motivation,
our ER program is entwined with the English syllabus using blended learning.
Students not only read books freely, but carry out productive tasks such
as writing exercises, presentation, video creation, use of AI and stage
performance. All aspects of this approach contribute towards grading and
parents are also able to see progress at every step. Longitudinal analysis
has also shown evidence of improvement in reading and especially listening
and writing skills over the past five years.
11:30-12:30 賛助会員各社による多読図書・サービス紹介(録画映像)
XLearning Systems(9min.)
Nellie’s English Books(9min.)
コスモピア株式会社(9min.)
株式会社トライアログ・エデュケーション(4min.)
株式会社ドリームブロッサム(4min.)
株式会社mpi松香フォニックス(4min.)
ピアソン・ジャパン 株式会社(4min.)
12:30-13:30 昼食・休憩
13:30-14:00 ポスターセッション 花元宏城(東京電機大学)
共同発表者:飯島悠矢、髙橋知暉、山中伸也(東京電機大学)
多読内容伝達における自発的ジェスチャー使用
本発表では、YL1.0以下の多読内容を相手に1,2分で伝達する際の、発話と共に用いられる自発的ジェスチャー使用に焦点を当てそれらにどのような種類・機能があるのかを明らかにする。観察の結果、多読内容伝達で用いられる自発的ジェスチャーには発話産出型だけでなくコミュニケーション・相互作用型使用も多々見られた。発表ではこれまでの多読活動運用面だけでなく、発話実験での実例を参加した学生と共に紹介したい。
14:00-14:30 実践報告 鄭京淑(ArcoS English Tadoku Square)(録画映像)
共同発表者:濱﨑志保、中川尋子(ArcoS English Tadoku Square)
「英語のスキーマ」を育てるプレ多読の実践とその成果・課題
小学校低学年は、英語の音声やリズム、語彙の習得にとって極めて重要な時期であると捉え、サイトワード(視覚的認識とスキーマの養成)とフォニックス(音と文字の対応)を組み合わせた指導を、学習者の興味・関心に応じて選定できる多様なレベル・ジャンルの多読図書と、語彙定着や理解促進のためのワークシート、オンライン教材などを活用した多読サポートの実践の成果と課題について報告します。
14:30-15:00 研究発表 大重のり子(フェリス女学院大学)(録画映像)
How Extensive Reading and Explicit Vocabulary Teaching Help Writing for
University Students
本調査では日本人大学生のwriting クラスに、授業内多読と明示的な語彙の指導を取り入れwriting のfluency, accuracy,
complexity を観察した 未読了者25% の学生のaccuracyは低く、3人称単数動詞形、代名詞、接続詞などの項目で間違いが顕著に見られた fluency,
complexityの伸びも読了者75% に及ばなかった。
15:00-15:30 実践報告 笠巻知子(京都外国語大学)(録画映像)
共同発表者:吉田真美(京都外国語大学)
『読まされる』から『読みたい』へ:自律的な多読への新たな試み
本実践報告では、京都外国語大学の多読プログラムにおける新しい試みとその効果について考察する。「紙の本での多読の導入」と「目標達成以外の評価方法」の2本柱を特徴とする新しい指導方針を導入した。教育実践方法や工夫(評価基準や管理方法の変更、紙の本での導入、教員養成やリソースの整備、学習促進活動)が、学習者の動機づけや自律的学習だけでなく、教員の多読への意識に与えた影響について実践的に考察する。
15:30-16:30 パネルディスカッション(パネラーは発表者)
16:30- 事務連絡、閉会のあいさつ